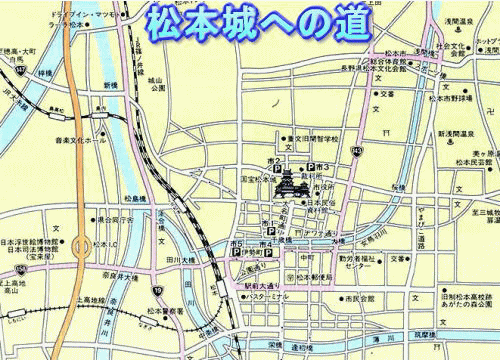
| 独善!!ゆうさんのこれが正しい 松本城への道 |
目次に戻る( return to the page of contents
)
英語ガイドへ( to an English page )
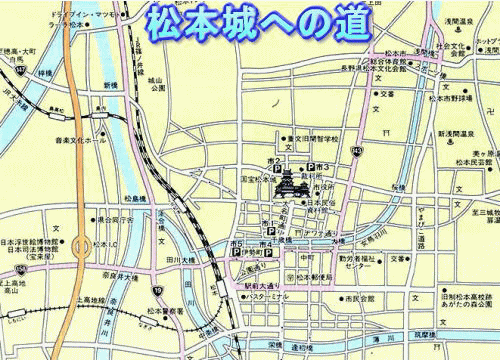
 松本駅より駅前通  深志二丁目ここで左折 |
松本城を訪れるならマイカーよりもJRをお勧めします、何故なら松本城は天守群の建物のみでは無いからです。松本城に来る大半のお客様は観光バス、修学旅行、それにマイカーの方々で、いずれも埋見の橋(昭和年間に観光用に造られた赤い橋)側の市営駐車場に止めて、長くても一時間のスケジュールの観光でこの素敵な建造物をただ登って降りると言うなんとも味気ない楽しみ?方で通り過ぎて行きます。この様な方々のなかには、なぜこんなに階段が狭くて、段幅が広くて、急なのか!!エレベーターは無いのかとまるでトンチンカンなことをおっしゃる方もいて、なんとも寂しい限りです。尚、間違えてこの駐車場に止めてしまった場合は少なくても、赤い橋側の切符売り場からは入場せず、外堀を東に回り込み太鼓門を経由して黒門側の切符売り場より入って下さい。ずーと得した気持ちになれますよ。 さてJR松本駅東口をでたらそのまま大通りを東にスクランブル交差点(深志二丁目)まで直進して下さい。(お車の方はこの交差点東北の位置に有料パーキングがありますからここを利用)この交差点を左に進みます。この通りは本町通りと呼ばれ松本城下町の3親町の一つです。今は松本市街地の再開発中ですが江戸時代は商人町で問屋が多かったらしいです。 |
 牛つなぎの石  中町との交差点 |
しばらく歩いていくと本町の枝町である伊勢町との交差点左手に注連縄飾りの石が祭られています。戦国時代、武田信玄と上杉謙信が長野県を舞台に戦った時、静岡県の今川義元が戦略で武田氏への塩の供給を断ち、松本近在の人々は大変困りました。上杉謙信はこれは人道上無視できず、糸魚川・大町経由で塩を送ったそうです。塩は牛の背中に付けられて松本には1568年1月10日に到着してそれを記念して塩市が始まり後に飴市となったそうです。この石に牛の手綱をまきつけたことから、後に”牛つなぎの石”となずけられたそうです。 さらに進みますと右手にT字の交差点があります、この道は中町と呼ばれ親町の一つです、商人、職人の町でした。今は古くからの土蔵造りの建物を保存しながらそのイメージで再開発が進められ、松本民芸家具のショールーム、蔵の町会館、秤の博物館、その他骨董品店、みやげ物屋などぶらぶら歩くには楽しい通りです。 |
 千歳橋より大名町を望む |
さて大きな新しい橋が見えてきました、千歳橋といいます。架かっているこの川は女鳥羽川です。橋を渡った向こう側の道路がクランクしてますが、川と平行に総掘りがそして丁度その位置に大手門がありました。高さは正面の八十二銀行のビルの3階位のものでしたから随分大きな物でした、イメージを膨らませると楽しいと思います。右手川沿いの通りは縄手通りで小さなお店何軒か並んでいます。昼間は歩行者天国ですのでぶらり歩きにはいいかと思います。 |
 大名町通 |
橋を渡るといよいよこの通りからは昔でしたら城内です、大手門は番所が置かれ武士以外通行許可の無い者は通行できませんでした。今歩いてる道路は大名町と言いますが当時は道の両サイドに高級大名の屋敷が立ち並んでいました。 |
 ここで真っ直ぐ行く人は正しくありません!! |
松本城天守が見えてきましたが、ここからまっすぐ黒門へ行く方は正しくありません、ここで外堀沿いに右に迂回します。少々天守までは遠回りですが、まず太鼓門を通りましょう!! 太鼓門の詳しいガイドは写真をクリックして下さい。  |
 天気の良さとカメラマンの腕にもよります |
太鼓門を楽しんだら、いよいよ黒門へ向かいます、内堀の錦鯉、白鳥など楽しんでください。また、天気が良い時は黒門へ入るまえの左上方に常念岳とセットの天守群は絵になります。 |
 鯉、白鳥、鴨、鳩、一瞬の合体 |
いよいよ切符を買って本丸庭園へ。その前にお堀の錦鯉と、白鳥さんを楽しみましょう、左の写真はゆうさん十年目にして初めてであったタイミングでした。  白鳥さんの昼休み |
 黒門、西側より望む |
切符売り場は黒門枡形内です、営業時間通常8:30am〜4:30pmまで大人一人600円(民族資料館入場料込)です。 黒門は昭和35年に、二の門と塀は平成元年に復興されました。まだ予算が掛けられず、資材も不足していた頃の復興でしたので黒門の柱などはベニヤのはりぼてです、叩いて見て下さい、空洞の音がします。復元された太鼓門の造りとは随分出来が違うのがわかります。 塀の造りが屏風型で折れ折れになっています、これも防御用の造りの一つです。 後は本丸庭園ガイドへどうぞ |