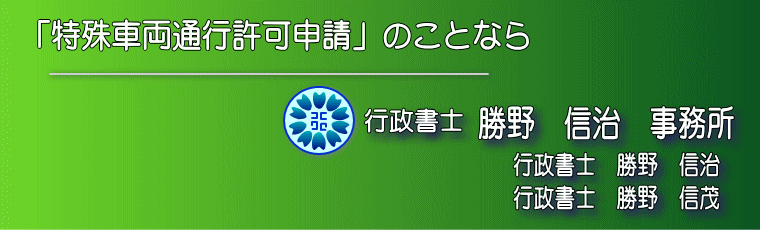
特殊車両通行許可制度について
特殊な車両(セミトレーラー等)を通行させようとしたときは、通行しようとする道路の管理者に申請し、許可(特殊車両通行許可)を得なければなりません。
道路法に基づく車両の制限
一般的制限値
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
|---|---|---|
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長さ | 12.0メートル | |
| 高さ | 3.8メートル | |
| 重さ | 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
|
| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル | |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。
指定道路
一般制限値を超えた重量、高さを決めた道路のことです。指定道路については迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には案内標識が設置されています。
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
■車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
詳細については下記リンクをクリックして下さい。
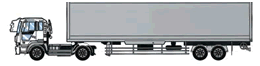 特殊な車両の主な種類
特殊な車両の主な種類
■貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
特殊車両通行許可申請
オンライン申請
当事務所ではオンライン申請を実施しています。
申請に必要な書類
申請には、次の書類が必要です。
| 書類名 | 作成部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 特殊車両通行許可申請 | 1部 | |
| 車両に関する説明書 | 1部 | 新規格車については不要 |
| 通行経路表 | 1部 | |
| 経路図 | 1+申請車両数 | |
| 自動車検査証の写し | 1部 | |
| トラック・トラクタ内訳書(注) | 1+申請車両数 | |
| トレーラ内訳書(注) | 1+申請車両数 |
申請書類(自動車検査証の写しを除く)については、インターネットを利用したオンライン申請システムで作成することができます。
なお、上記の書類の他に道路管理者が必要とする書類については、提出しなければなりません
■普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
※申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。
※複数軸重の申請は、寸法(幅、長さ、高さ)のみ申請できます。なお、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸重申請はできません。
■通行期間を延長したいとき
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
■申請内容を変更したいとき
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
■往復または片道で申請したいとき
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。
■往路と復路で車両の状態が異なるとき(積載状態または空車状態)の申請
□往路,復路とも一つの申請とする場合
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
□片道ごとに二つの申請とする場合
積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。
許可申請の流れ
許可申請は当事務所が代行します。ご依頼頂けば通行許可証をお届け致します。
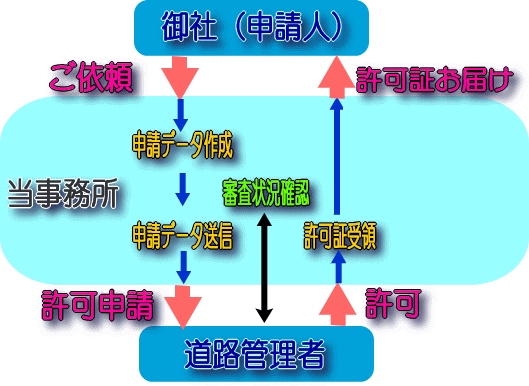
手数料
■手数料とは
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。その額は、国の機関の窓口では200円(1経路)、県の窓口では、条令によって多少異なる場合があります。
■手数料の計算方法は
申請車両台数×(申請経路数)×200円
と求めます。
申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数とします。
《6ルートを申請する場合》
6ルートを往復申請すると、申請経路数は12経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が4台のとき 4台×(12経路)×200円=9,600円
なお、片道申請の場合は、申請経路は6経路として扱われます。