アマチュア無線
更新日 2001.1.8
現在のシャック
真空管が現役で働いています
TX310、JR310 1973年から 

TS820 1977年から 
名機も現役で働いています
IC−551 TS−700 IC−390

現在のアンテナ
 50MHz HB9CV 4−EL
50MHz HB9CV 4−EL
44MHz 10−ELスタック
430MHz 15−ELスタック
1200MHz 8−EL デルタループ 8パラ(自作)
144/430MHz コーリニア
 7MHz/3.5MHz ダブルDP
7MHz/3.5MHz ダブルDP
給電部 9メーター 傾斜形
 HF バーチカル 現在は28/21/14MHz用
HF バーチカル 現在は28/21/14MHz用
極めて能率が悪い
いくつかの工夫を紹介します。
モービル運用
ホイップアンテナ(スパイラル)
通常のソレノイド上のコイルとは一味違ったくもの巣(スパイダー)または、スパイラル
出典はCQ出版社のモービルアンテナの本にあり、写真から再現したもの。
通常のモービルホイップに見られるコイル部分での機械的強度補強の必要がない、極端に言えば ついていればよい。


ちょっと見にくいかもしれませんが、運転席窓枠から斜めに突き出たアンテナ。

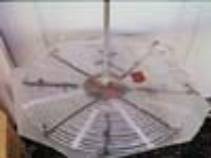
通常運用のアンテナ 半固定でのアンテナ

ラジアル
コイルを巻く導体の長さは、だいたい短縮する長さ分を巻けばよい。
通常運用では小さくするためにホルマル線を使用(1mm)
半固定ではスパイラルの理論から作ったもので、当初はこのスパイラルは天辺についていた。しかし、トップヘビーで走行不可能のため下に下ろした。

自慢の軽自動車用基台(アルミ2.0mm)
なぜか、軽自動車のためのアンテナ基台がない
仕方がないので、2mmのアルミを加工して作った。これまでに、走行中に2回ほど落下したことはあったが、十分実用に耐えると考えます。

有り合わせで作ったアンテナチューナー
一気に1.0まで
ラジアルは10m長をぐるぐると車体に巻く
アクリル板に組み立てて、シールドもなしにこのまま助手の下に置いて使用
HFマルチバンド調整可能であり、ホイップなどのようにインピーダンスの低いアンテナの調整では、クリップの位置をSWR計をみながら選択していくとみごとに
1.0まで下げられる。
スパイラルアンテナ
(ダイポール+スパイラル)
詳しい理論については不明ながら、W誌の抄訳に基づいて再現実験を試みて、十分満足のいく結果が得られた。
7Mhzダイポール+3.5Mhzスパイラル
7Mhzダイポールしか張れない敷地で3.5Mhzダイポールに匹敵する実績
20mワイヤーの両先端に3.5Mhz用のスパイラルを取り付ければ7/3.5の2Bandアンテナの出来上がり
3.5Mhzスパイラルの作り方
一般的な話では、1/4λ長の導体をらせん状に巻いていけばよい。
したがって、3.5Mhzの場合は 約20m の アルミ線を巻き調整により同調させる。
調整段階では、帯域幅 3.5Mhz帯びでは 20khz程度と苦しいが、CW運用などでは気にならない。
なお、帯域内では 通常のダイポールアンテナと比較してもほとんど引けを取らない実績が得られた。
実際に建てた写真



7Mhzダイポールに3.5Mhzスパイラルを取り付けたところ
データ(調整段階のデータ、天候、気温によるSWRの変化)
7Mhzで1.1
3.5Mhzで1.3 の実績
3.5Mhzはダイポールに引けを取らない
最大の欠点は、天候による影響が大きいこと
これまでに実験してきた
スパイラル群


3.5Mhzスパイラル 3.5Mhz 7Mhz
アルミ(左)、ビニール電線(右)

21Mhzスパイラル
スパイラルを巻く治具


巻き始めの導線をはさむ部分
2枚の基盤を軸上にセットし、あとはひたすら導線と紐をいっしょに巻くだけ
データのページ
データを用意しました。とりあえず SWR特性
必要な方は ここを クリックしてください。