2011(H23)-05-10�@�����̉� (�l���Ă�����H�})����߂��n�C�u���b�h���Ɍv��ύX���܂����B
�����g�n�ƒ��Ԏ��g�n��^��ǁB������H���̉����܂��B |
|
���܂܂ł̐i���B�@���i�Ɣ����̂̑��������������悤�ŁE�E�E�E�E�E�B
�y�ʐ^�@�����z�@���g���J�E���^�܂Ŋ���
�y�ʐ^�@�����z�@�e�d�s �Q�r�j�P�X�Q�̋ǔ����������B���C���o���R�����̓t���C�z�B�[�����y���̂ł���Ȃ�̃t�B�[�����O�B
�y�ʐ^�@���E�z
|
|
|
���g���J�E���^�܂Ŋ��� |
|
������ |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
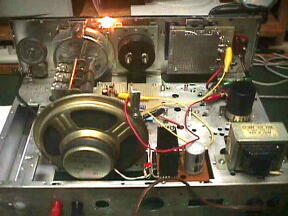 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(H23)-05-11�@�ۊǂ��Ă����v�����g��̑g�ݕt���Ɛ^��ǃ\�P�b�g��t�� |
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@�ǔ��ǂU�`�p�W�����C���o���R���ɓ�����̂Ŏ�t�����C���@�R�����قNJ��B
�y�ʐ^�@�����z�@�W�����N���i���p�����ሳ (�{�W�u) �d�����
�@�@�@�@�@�d���g�����X�ɂU�D�R�u���������Q�g����̂őS�g������H�ɂ��Ă���B
�y�ʐ^�@���E�z�@�������B�B�e���O�A��d�����d�ǂO�a�Q�j���B����E�������̂��ق��������B
|
|
|
�^��ǂ��Z�b�g�����݂� |
|
�ሳ�����d����� |
|
������ |
|
|
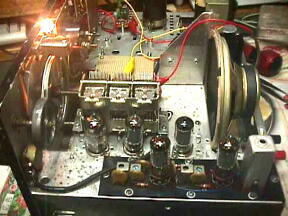 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@��d�����d�ǂ̐Ւn
�y�ʐ^�@�����z�@�����g���ƒ��Ԏ��g�v�����g���
�y�ʐ^�@���E�z�@�X�v���b�h�o���R��
|
|
|
�{���̓d���g�����X |
|
�^��Ǖ� |
|
�X�v���b�h�o���R�� |
|
|
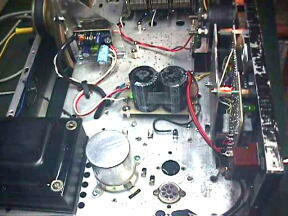 |
|
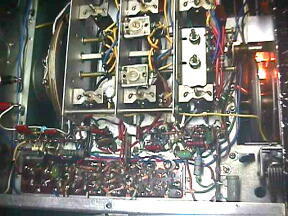 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-05-12�@���Ԏ��g�̒���
�s�v�c�Ȃ̂̓��J�j�J���t�B���^�ɂ�������炸�h�e�s���ɒ����R�A������s�[�N�����邱�ƁB
���J�t�B���^�Ȃ̂ŕ����d�g��M���ăs�[�N����邾���B�ȒP�A�ȒP�B���J�t�B���^�����ꂢ�ȃs�[�N������B
�y�ʐ^�@�����z
�y�ʐ^�@�����z�@��H�}�ɂ��w�l�e�x�Ƃ��邪�����R�A������̂��s�v�c�B
�y�ʐ^�@���E�z�@���N�O�t�����X�g�A�������ۂ̃��J�j�J���t�B���^�g�ݍ��݂����J�t�B���^���W�I�B���g�ǂ������{�R�d�l���g�ǁ@�U�g�U�`
|
|
|
������ |
|
���J�t�B���^�Ƃh�e�s (�����R�C��) |
|
���ۂ̃��J�t�B���^�ƂU�g�U�` |
|
|
 |
|
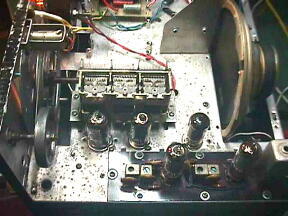 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�y�z���}�z
2011(H23)-05-19�@��H�萔�ύX�@���̉�H�}�͑g������̂��̂ł��B
�傫�ȕύX�_�́{�a�d���͂P�T�O�u����P�P�T�u�ɉ��������ƁA����Ńg���I�̌���H�̓d���ɂȂ�܂����B����0B2��t���ȂǁB |
|
|
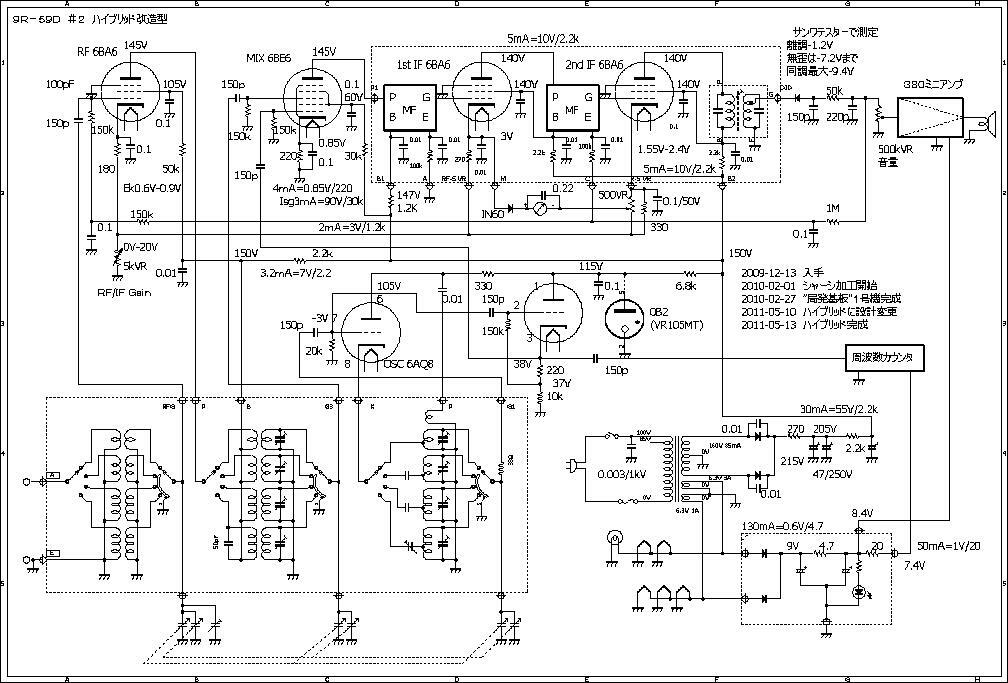 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-05-13�@�����x�ׂĂ݂܂����B�����ʂ̓��[�^�[�̓ǂ݂ł��̂ŎQ�l�ł��B�W�U�S���g���͓��n�̖����@�M�z�������{������
�Q���g�������@�@�@�|�Q�Q���a�^�Q���g���̌��� |
|
|
��2kHz�����@862kHz�@+7dB |
|
�����@+32dB |
|
��2kHz�����@866kHz�@+10dB |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
�@�@-25dB/2kHz |
|
|
|
�@�@-22dB/2kHz |
|
|
|
|
|
�R���g�������@�@�|�Q�T���a�^�R���g���̌��� |
|
|
��3kHz�����@861kHz�@+5dB |
|
�����@+32dB |
|
��3kHz�����@867kHz�@+7dB |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
�@�@-27dB/3kHz |
|
|
|
�@�@-25dB/3kHz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(H23)-05-15�@�@�d�ɓd���������Ȃ̂Ńg���b�L���O�����͂��ꂩ��B
�P�@�r���[�^�[���U��Ȃ��Ȃ����̂Ō��g�_�C�I�[�h�������J��Ԃ������r���[�^�[�̐U�ꂪ�݂��Ȃ����B
�Q�@�R�W�O�A���v�̓d���d�����{�W�u�Ȃ̂ő剹�ʂɂȂ�Ȃ��B
�R�@�b�o���h�̒��ŋǔ���~����B
�S�@�NJԃm�C�Y���������̂Ŋ��x�����܂�ǂ��Ȃ��Ǝv���B
|
|
|
2011(H23)-05-19�@��H�萔�ύX�@0B2��t���B
�P�@��g�_�C�I�[�h���P�m�U�O�Ɍ����B�`�u�b�d�����肵�Ă���B
�@�@�@�������A��L�̂Ƃ��茟�g�Ɏg�����W�����N�܂�����o�����_�C�I�[�h�̋����������������̂Ő��K�i���w���������́B
�Q�@�{�a�d�����P�T�O�u�ƍ��������̂ŕ�����R270���Q�k��820���T�k�Ɍ����B�{�a�d���͂P�P�T�u�ƌ���H�}�̒l�ɂȂ����B
�R�@�O�a�Q���͒�R��1k���p���B���艻�d���P08�u�B�d���~����R900����7V�B���̎��̓d����8mA�B
�S�@�h�e�s�A���J�t�B���^�Ē����B���ꂢ�ȃs�[�N����ꂽ�B
5�@�g���b�L���O���� |
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@[���W�I���N] �ɒ����������i�����B0A2�A0B2�A5Z2P(5Y3GT������)�A1N60�ȂǁB
�y�ʐ^�@�����z�@��d�����d�ǂO�a�Q�B�ǔ��{�a�̈��艻�p�A�@�����Ŏ������Ă��������g�тł͈��肵�Ă����B
�y�ʐ^�@���E�z�@�g���b�L���O�������@�Z�g�т͈ȑO�����������s�[�N�̂Ƃ�Ȃ������ӏ�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���m�o���h�T���X�[�p�[�̓`���C�`���C�����ǂS�o���h������Ƒ�ρB�Q�O���͂�����܂��B |
|
|
��C�p���i |
|
0B2(VR105MT) |
|
�g���b�L���O������ |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011(H23)-05-19�@����
�y�������z
�P�@���@�f�W�^�����ǂ����K�B�E��Ń��C���o���R���A����ŃX�v���b�h�B���R�ɖڐ��͎��g���J�E���^�Ƃr���[�^�[�Ǝg���Ղ��B
�@�@�@�@(����͓�������l���Ă������ƂłX�q�|�T�X�c���^�̓��C���ƃX�v���b�h�������c�}�~�͎g����v���Ǝv��)
�Q�@���@�����x�͗ǂ��ē��R�B���x�����P���Q�Ƃ��Ă͍��i
�R�@���@���J�t�B���^�̂��߂������悪�J�b�g���ꂽ���B�����₷�����ł͂��邪�B
�S�@�~�@�����p�h�b�R�W�O�A���v�̋����d�����{�W�u�Ȃ̂ʼn��ʂ��������B
�T�@�~�@�����̉����ď��^�A�y�ʂ̒ʐM�@�^��M�@�������肾�����A�d���g�����X�����p�����̂ŏd���B
��Ԃ́~�̓I�[�������̉��Ɏ��s�������ƁB�ڕW���qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�������̂����ǁB
|
|
|
�P�@2011(H23)-05-13�@�n���_�t���I���B�ʓd�A�ꔭ�Ŗ����B
�@�@�@���g�p�Q���_�C��������Ȃ��̂ŃV���b�g�o��(�X�����D�ɂ�ERA82�Ƃ������悤��)���g�p�B�`�u�b-7V����
�@�A�@�P���Ԃقǎ������A�r���[�^�[���U��Ă��Ȃ����ƂɋC�����B���Ă��邪�`�u�b�d���|�O�D�Q�u��
�@�@�@�@�@�q�e�^�h�e�����ǃJ�\�[�h�d���������A�������Ă��ω����Ȃ����Ƃ��m�F�B
�@�B�@�Ȃ��[�_�C�I�[�h�̕s�ǂ��E�E�E�E�莝���̃W�����N�܂���Q���_�C�炵������(W06�ƕ\��)�_�C�I�[�h�����@���@�`�u�b���������B
�@�C�@���傤�Ȃ��Ȃ��B�܂��_�C�I�[�h�����@���@�`�u�b���������I�E�E�E�H
�@�@�@�@�@�_�C�I�[�h�O�̉�H�͖��Ȃ����Ƃ��m�F�̂��߃V���N���łh�e�s�o�͂Ɖ����M�����x���͐��u���m�F�B
�@�@�@�@�@�w��͂�W�����N�ܕ�������ʖڂ��A���x�̓e�X�^�[�Œ��ׂĂ���x�����@���@�`�u�b���������H�H�B
�@�@�@�@�@�w�A�����@�@���������_�C�I�[�h�����������Ȃ����x�H�H�H�B
�@�D�@�����ɇ@�ƈႤ�V���c�g�o���Ɍ���������`�u�b�������Ă��邱�ƂɋC�������B�邪�`�u�b�d���Ⴂ�B
�@�@�@�@�@RF/IFgain���i���Ă��邱�ƂɋC�����l�`�w�ɂ�����`�u�b�d�����o���悤�ȋC�������B
�@�@�@�@�@�`�u�b�d�����ቺ���_�C�I�[�h�������Ă����Ȃ��̂ŃV���N���łh�e�s�o�͂Ɖ����M�����x���͐��u���m�F�B
|
|
|
�Q�@5/14�@��������d�����d�ǂƃQ���_�C���l�b�g�ɂĔ��� |
|
|
�R�@5/19�@�����������i���� |
|
|
�S�@2011(H23)-05-19�@���g�_�C�I�[�h�@1N60�Ɍ����@�`�u�b�d�������@ |
|
|
�T�@5/21�@�ǂ����W�����N�܂̃_�C�I�[�h���������̂� [���W�I�H�[�f����] �Ɏ��� |
|
|
�U�@2011(H23)-05-22�@�_�C�I�[�h�̎��������Ă݂܂����B
|
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@�W�����N�܂�����o�������g�p��g�p�����_�C�I�[�h�ƐV�K�w�������P�m�U�O
�y�ʐ^�@�����z�@�h�e�s�̃z�b�g�[�q����ԐF���j�����A�����A�`�u�b��o���_����ΐF���j�����Ń_�C�I�[�h�������Ă݂�B
�y�ʐ^�@���E�z�@���̂܂����������ʂ������Ă��� |
|
|
�@�e��_�C�I�[�h |
|
�������@�`�u�b�d�����蒆 |
|
|
|
|
 |
|
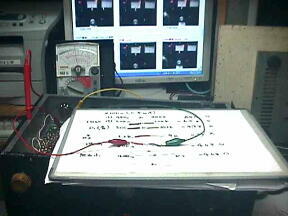 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�@
|
�_�C�I�[�h�̖��̂Ȃ� |
�V�i/���Õi |
��������R (��) |
�t������R (��) |
�@��/��Ȃ� |
�`�u�b�d�� |
�@�@�@���l |
| 1 |
�P�m�U�O�@����1 |
�@�g�p�� |
�@�@�@450 |
�@�@�@200k |
�@�@�@�� |
�@�@-6V |
|
| 2 |
�P�m�U�O�@���̂Q |
�@�V�i |
�@�@�@500 |
�@�@�@100k |
�@�@�@�� |
�@�@-6V |
|
| 3 |
�W�����N�܂̕i�@�F |
�@���Õi |
�@�@�@500 |
�@�@�@300k |
�@�@�@�� |
�@�@-4.7V |
|
| 4 |
�W�����N�܂̕��@�a�Q |
�@5/15��O�i�H |
�@�@1,200 |
�@�@�@�@7k |
�@�@��Ȃ� |
�@�@-0.3V |
|
| 5 |
�W�����N�܂̕��@���� |
�@���Õi |
�@�@�@800 |
�@�@�@���ɋ߂� |
�@�@�@�� |
�@�@-4V |
|
| 6 |
�W�����N�܂̕��@�����@1 |
�@�V�i |
�@�@�@400 |
�@�@�@���ɋ߂� |
�@�@�@�� |
�@�@-4V |
|
| 7 |
�W�����N�܂̕��@�����@2 |
�@�V�i |
�@�@�@700 |
�@�@�@���ɋ߂� |
�@�@�@�� |
�@�@-3.7V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�S�Ԃ̃_�C�I�[�h�ȊO�A�Ⴂ�Ȃ���`�u�b�d�����������Ă���B�ǂ�ȃ_�C�I�[�h�ł����g�Ɏg����B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011-05-24�@�y����(���̎���������Ηǂ�����)�z
�P�@�s�����̏������m�F���邱��
�Q�@�_�C�I�[�h�̐����@�\�̊m�F�����R�����W�ł����̂Ō������ɔj�Ă����H�B
�@�@�@�莝���̃e�X�^�[�͒�R�~�P�����W�̑���d����15mA�B�~�P�O�����W��1mA�B�E�E�E�E�P�T���`�ł͔j�ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ����B
�R�@RF/IFgain���i���Ă������ۂ��́A�`�u�b�d�����Ⴏ��Γ��R�A���ӎ���gain���ő�ɂ���͂��B
���܂̂Ƃ��뎎�����Ă��邪�Ǐ�͏o�Ă��Ȃ��B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
�y�Q�l�z |
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@�莝���̓h�����������Ȃ������̂ŁE�E�E�E�E�E
�y�ʐ^�@�����z�@������莝���̃S���������t������B���莞�͑����P�{���A�P�{�j������قǂ̗����Ռ��̍��Ղ��������B
�y�ʐ^�@���E�z�@���Y�̂n�d�l�i���qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@
|
|
|
�J�o�[����t�� |
|
��̎��t�� |
|
����́@�qeali���������@�c�w�|�P�U�O |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�\���b�h�X�e�[�g�ʐM�@�^��M�@�@���^�E�y�ʁA�ȃG�l |
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@TRIO R-300�@�@�w�i�̃p�\�R�����j�^�[���t���ɂȂ��Ă��܂��i�@�}�j�A���L
�y�ʐ^�@�����z�@KENWOOD R-2000�@�}�j�A���L
�y�ʐ^�@���E�z�@�qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�̃v�����g��B�z���}�Ƃ���̊�Ȃ̂ʼn�H���ǐՂ��₷���B�}�j�A���L
|
|
|
TRIO R-300 |
|
KENWOOD R-2000 |
|
�qeali���������@�c�w�|�P�U�O�@�̓��� |
|
|
 |
|
 |
|
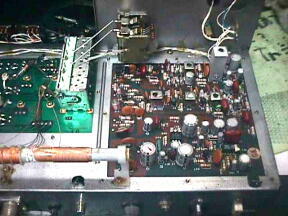 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@Lafayette BCR-101�@�n�d�l�ō���Ă�������B�}�j�A���L
�y�ʐ^�@�����z�@KENTEC BCL-1�@�������B�@(�S�I�[�i�[���_�C�A�����C�g��F�Ɍ������Ă���)�@
�y�ʐ^�@���E�z�@���@�킨���Ȃ��郁�C���o���R���V���t�g�B�c�O�Ȃ��珊�L���Ă���BCL-1�͋Ȃ����Ă��Ȃ������B
�@�@���̌Z���M�@�̉�H�͂��̂������Â��Ă�B���ʋ@�\�I�ɂ͂������� (����A�����ς�) �l���Ăق��������B�}�j�A���L
�@�@�����̐V�Z�p�����ʃv�����g������̗p�����܂ł͗ǂ��������X���[�z�[�����H���ĂȂ��̂ő��̃T�C�g�ł̓W�����p�[���̐X�B |
|
|
Lafayette BCR-101 |
|
KENTEC BCL-1 |
|
�o���R���̎����Ȃ��� |
|
|
 |
|
 |
|
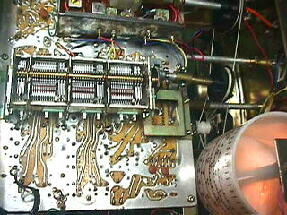 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|�|
|
|
|
2011(H23)-09-10�@���g���J�E���^���������܂����B
�f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�@�̉t���\�����Â��ď������̂Łh���l�̂����f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�h�ƌ��� |
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@�����O
�y�ʐ^�@�����z�@�f�s�ǒʐM�@�^�S�o���h��M�@�̉t���\���̎��g���J�E���^�B�Â��ď������̂Ō���B
�@�@�@�t���\�����������ʃp�l���̉��ɂ��肵�����o�b�N���C�g�����ʂ��������Ɍ���B
�y�ʐ^�@���E�z�@������
|
|
|
�����O�@�@�k�d�c�\���̂��� |
|
�����O�@�t���\�� |
|
������@�k�d�c�\�� |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
�y�ʐ^�@�����z�@�t���\���Ɍ����B����͉̂䖝
�y�ʐ^�@�����z�@�N�����@�q���������e�b�@�q�P�D�Q�P�@
�y�ʐ^�@���E�z�@���M���ʓd���@�|�S�T�O�j�����@-455���g���ƂȂ�ׂ����ȁH�@�P�ʂ́h�j�����h�͐ق��B�@�h���g���h�ɂ��ׂ��B
|
|
|
������@�t���\�� |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
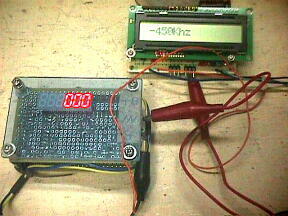 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|