ページ1
| 本丸庭園出会いから、外観を見てのご案内!! | |||
| 始めまして松本城ボランティアガイドです。宜しかったら無料でお城の案内をしますが、如何ですか。そうですか、丁度ガイドが欲しいと思っていらしたのですか、それではご一緒にいきましょう。どうでしょうこの素晴らしい建物は、松本城の天守群の造りは連結複合式と呼ばれているんですが文字どうり幾つかの建物が結合されているんです。ご覧のように向かって右から乾小天守、渡櫓、大天守、辰巳附櫓、月見櫓と五つのユニットからなっています。 大天守の高さ約29メートル、石垣の高さ約3メートル、大阪城や姫路城と比較するとかなりサイズの上で見劣りしますが、素晴らしい建築美ではありませんか。 小天守、渡櫓、大天守初期の建造は1593年〜1594年とされています。豊臣秀吉が小田原城を落とし、徳川家康を関東に追いやって、天下統一を果たす頃にあたります。秀吉は関東に睨みを利かせる戦略的ライン上のお城の一つに松本城を決め、信頼のおける石川数正を松本城に送りました、数正は城の整備に精を出しましたが、文禄の役の出陣の折病死、その後息子の康長が城普請を引き継ぎ造られました。 この頃の日本はまだ内戦が残り、城そのものの造りも防御を重んじるものとなっています。実際問題として城全体が3重のお堀で囲われ、さらには塀が巡らされ、各門には番所が置かれまして、それだけでも十分なのですがあえて天守という高い建築物をしかも襲われた時の防御まで備えてつくり上げたのは城主の権力を示すとか、それなりの意味があったのでしょう。 壁の正方形と長方形の穴を見てください、鉄砲狭間、矢狭間と呼ばれるもので名の通り、穴の中より鉄砲や弓矢を撃つために作られたものです、トータルで100以上あります。松本城より後に築城されたもののなかには、円形、三角形、その他蓋付のものあります。 ここで質問があります、ここから見ますと、大天守の屋根は五層あります。さてこの建物何階建てでしょうか?大抵のお城の場合見た目より多いのが通例です、松本城大天守は六階あります。乾小天守は三階に見えて実は四階あります。 近くによりますと分かりますが、一階のコーナーと真中へんが少し出っ張って造られていますよね、これは石落としと呼ばれる防御で下に穴が空けられていてそこから文字どうり石垣を登ってくる敵に石を落としたり鉄砲、弓矢を放つのに使われるように造られたものです。 築城400年を過ぎた建物が良くこんなにいい状態で保存されていると感心されると思います、皆さんよくそうおっしゃられますが、実は明治に一回、昭和に一回大修理が行われています。昭和の大修理は1950年より足かけ7年を費やし、建物は全て、石垣も部分的に分解調査の上修復出来る物は修復し出来ないものは出来る限りオリジナルに近い形で復元をしました。戦後間もない頃の物資も機器も現在とは大違いの頃の仕事で、記録写真や文献を読むと大変な苦労の跡が分かります。もう一つ忘れてはいけないのが碇屋漆器店の先代とその息子さんの現店主の存在です、先代におきましてはまるきりのボランティアで建物のメンテナンスをして頂き、現在はその息子さんが毎年秋口の観光シーズン終わりごろ、ご苦労をいただき漆の塗りなおし等のメンテナンスを引き受けていただいています。 昭和の大修理の時にこの石垣の中を調査していると、1.5メートル位の朽ちた木片が見つかりました、調査を進めるうちに、このかけらが土台の中で建物を支える為に作られた16本の土台支持柱の一つの物であることが分かりました、今では16本の柱はコンクリートに置き換えられいますが、これらの支持柱なしでいた当時の天守の傾きは人の目にも明らかであったそうです。それは無理もない事だったのでしょう。この朽ちた木片は保存処理がされてガラスケースにはいって大天守1階に展示されています。 さていよいよ、建物の中に入ります、配られている袋に靴を入れて出口までお持ち下さい。建物内は暗く、階段の幅が広く急ですので足元に注意をお願いします。尚お配りした靴入れ袋は環境汚染を考慮して石灰より作られたもので自然に帰る素材で出来ています。 こちらをご覧下さい、この蓋を開けると石垣が見えます、現在この石落としの蓋のみ開けて下を見ることが出来ます、大天守の1階の西側の物も網がはられて下を見れるようにしていますが。 英文ガイドはこちらから |
向かって右から乾小天守、渡櫓、大天守 辰巳附櫓、月見櫓 乾小天守と大天守が渡櫓で連結され 大天守と辰巳附櫓、月見櫓が複合的に造られ、連結複合式と呼ばれる特異な構造です。 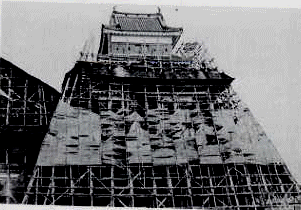 昭和の大修理 足場には丸太材が使われた 土台支持柱の残片 保存処理されてガラスケースの中に 石落とし内側より、トイレとして使われたか? |
||
| 乾小天守内一階と二階,渡櫓のご案内!! | |||
| 建物に入られて第一の感想はどうですか。皆さん暗いとか柱が多いとかトイレは無いんですかとか言われます。 この乾小天守内の柱はどういう訳か丸柱が何本か使用されています、これは他の四つの建造物には見られない特徴の一つになっています、ここで質問ですがこれらの柱の表面の削り具合はいかがですか、どんな道具を使用していると思いますか。手斧(チョウナ)と呼ばれる道具で削られています。使われている木材の種類は、栂、檜、欅、サワラ、ネズコ等となっています。 それでは二階に行きましょう。内部の階段は狭く急勾配に作られています。足元に注意してお登りください。理由は簡単ですよね、敵が侵入した場合攻めにくくしてあるんです。(本当は建築構造上柱間の寸法で勾配が決まっているようです。)ところでこの天守内には人は住んではいませんでした、勿論内部にトイレはありませんでした、もしかしたら、石落としより用をたしていたのかもしれませんね。お堀の鯉が異常に肥えている訳がわかるような気がします。(笑い) さてここからはよく鉄砲狭間、矢狭間がいい感じで並んでいるのが見えます。よく見ますと内側のほうが外側より広く作られています、狙いやすく攻められにくいと言うことでしょうか。壁の厚さも見ることができます、階が上がるに連れて薄くなっているらしいです、これも堀の広さ同様に銃器による攻撃に備えて考えられているようです。ちなみにお堀の広さは大体50メートルだそうです。 こちらの縦格子の窓をご覧になってください、スライド式になっていますが引いてみてください、どうです結構重いでしょう、それに随分厚い材料で作られています、これは推測ですが、当時の火縄銃は玉込めに数分要したようですので、開けて射ち、閉めて玉込め、又開けて撃つの繰り返しをしたのでしょう。(最近はストッパーで動きを止められてしまって説明の時に実演が出来ません。) こちらの絵地図をご覧下さい、昭和年間に描かれたものですが、16世紀初めの頃の松本城を描いています。日本国内に造られたお城の建物は大きく分けてその場所により三種類に分類されます。山の中に造られた山城、丘の上に造られた平山城、そして松本城のように平地に造られた平城となります。平城は地理上攻められやすい、そのため防御ラインに堀を幾重にも巡らせました。内堀、外堀、総掘、さらにもう一重工事のとちゅうまで造っていたらしいです。更には女鳥羽川の東から西への流れを北より南、更にお城を囲むような流れに変え防御のラインにしています。この川の流れを変えることは更に南に流れる薄川にもなされたようです 一般的に松本城と言うと、天守群建物だけのように思われますが、この総掘に囲われた地域全体を称して松本城となります。一番内側のお堀に囲われている地域は本丸とよばれていますが、今私たちのいる天守群、それに城主大名と家族の御殿がありました、この本丸御殿は1727年正月台所より出火の火災の為全焼してしまいました。以後多分経済的な理由で再建はされず現在にいたっています。 内堀と外堀(二番目のお堀)に囲まれている地域は二の丸と呼ばれています、ここには二の丸御殿(本丸御殿全焼のあと、城主の居住区、行政の場所として使われた)、ほか各種倉庫(食料用、武器用など)が立ち並んでいました、さらに今、民族資料館の在る位置に古山寺御殿が建っており、城主の私的な離れとして使われていました。 一番外側の総掘と外堀の間の地域は三の丸と呼ばれ、高給大名の屋敷が並んでいました。城外より本丸内にたどりつくには三つの大きな枡形門を超えなくては進入できない構造に成っていまして、通常は武士以外の人々は通行が制限されていました。下級武士は城外の周り特に北側に居住して回りを固めていました。いっぱん町民は城外南側より東側に伸びる地域でその職業により大体の場所がきまって居住していました。 それでは行きましょう、こちらの狭い部屋は渡り櫓二階です、松本城はこの天守が出来てから六家二十三代の城主が治めました、こちらのガラスケースの屋根瓦の家紋をご覧ください右のものは六家の内の戸田氏の家紋です。 こちらの古屋根瓦の標本は昭和の大修理の時に見つけたもので幾つかの屋根瓦に住所やら名前やら日付けが書かれていました。これは150年位前の物でしょうか。 さていよいよ大天守一階へと進みます階段で下に下りますが降りた所に段差がありますのでご注意下さい。
|
矢座間鉄砲座間内側より 縦格子の窓、ほとんどの窓がこの様なつくりである 展示されている絵地図 展示されている屋根瓦他建築用材 |